
近未来教育フォーラムは2010年の初開催以来、デジタルハリウッドが擁する各教育機関(4年制大学、専門職大学院、専門スクール、オンラインスクール、ジーズアカデミー、デジタルハリウッドアカデミー)が取り組む教育実践の報告を通じて、これからの教育への提言を行ってきました。
近未来教育フォーラム2024のテーマは『The Great Transition~ポストAIは来ない~』。フォーラム本編となるキーノートでは「デジタル民主主義」を掲げるAIエンジニアの安野貴博氏、人工生命を研究する岡瑞起氏(筑波大学准教授)、そしてデジタルハリウッド大学大学院の藤井直敬卓越教授の3名が登壇し、「The Great Transition」における変化の予測と、人類がどのように文化を営み社会を築いていくべきかについて教育という視点で議論します。

『AIで世界は変わるのか?』 生成AI、また自律的に動くエージェントAIというものがどのように人間社会のコミュニケーションを変えてゆくのか?
安野貴博氏が実際に挑戦をした東京都知事選を一つの例に、いかにAIがさまざまな物事のやり方を変えてゆくポテンシャルがあるのかについてお話します。
「The Great Transition」の時代、創造性の概念が大きく変わろうとしています。本講演では、岡瑞起氏がArtificial Life(人工生命)研究から得られた知見と、Open-endednessの概念が、いかに未来の創造プロセスと社会のあり方を形作るかを探ります。
『The Great Transition~ポストAIは来ない~』というテーマに基づき、プレゼンターの安野貴博氏、岡瑞起氏、そしてデジタルハリウッド大学の学長補佐を務める脳科学者の藤井直敬卓越教授をお迎えし、三者対談を行います。

AIエンジニア、起業家、SF作家。東京大学、松尾研究室出身。
ボストン・コンサルティング・グループを経て、AIスタートアップ企業を二社創業。
デジタルを通じた社会システム変革に携わる。日本SF作家クラブ会員。
2024年東京都知事選に出馬、AIを活用した双方向型の選挙を実践。

研究者。筑波大学システム情報系 准教授/株式会社ConnectSphere代表取締役。
2003年、筑波大学第三学群情報学類卒業。2008年、同大学院博士課程修了。博士(工学)。
同年より東京大学 知の構造化センター特任研究員。2013年、筑波大学システム情報系 助教を経て現職。
専門分野は、人工生命、ウェブサイエンス。
著書に『ALIFE | 人工生命より生命的なAIへ』(株式会社ビー・エヌ・エヌ)、
『作って動かすALife - 実装を通した人工生命モデル理論入門』(オライリージャパン)などがある。

東北大学医学部卒業。同大学院にて博士号取得。
1998年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)研究員。
2004年より理化学研究所脳科学総合研究センター副チームリーダー、2008年よりチームリーダー。
2014年株式会社ハコスコを起業。
2018年よりデジタルハリウッド大学大学院教授。研究テーマは「現実科学」。
主な著書に、「つながる脳」(毎日出版文化賞受賞)「脳と生きる」「現実とは?」など。
「デジタルハリウッドの各教育機関より以下のテーマ講演を実施予定です。キーノート本編の前に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。
AIにより生成されたコンテンツは著作権法上どのように位置づけられているのか。また、授業過程において、生成AIおよびAI生成コンテンツはどのような扱いになるのか、基本的な解説を行います。

デジタルハリウッド大学特命教授、国士舘大学知財大学院客員教授、大阪工業大学大学院客員教授
東京大学文学部社会学科卒業後、朝日放送に勤務、著作権部長等。1999年から2010年まで文化庁の著作権の審議会で専門委員。2018年から社団法人日本音楽著作権協会理事。著書:「海の楽園パラオ~非核憲法の国は今」(あみのさん)「クリエイトする人たちのための基本からの著作権」(商事法務)など。
近年、生成AIの活用が注目されていますが、「クリエイターと生成AIに関する意識調査2024」(※1)では、「生成AIを積極的に活用したい」と答えた人は33.4%にとどまり、可能性を理解しつつも導入に迷う現場の声が伺えます。
(※1)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002444.000000496.html
そこで今回は、現役映像クリエイターの小泉薫央さんをお招きし、ビジネスの現場で生成AIをどのように活用しているか、具体的な事例とともにご紹介いただきます。
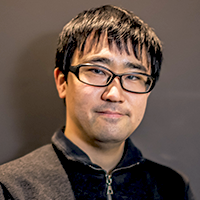
デジタルハリウッド大学大学院を卒業後、エフェクトアーティストとしてマーザ・アニメーションプラネットに入社、小島プロダクション(当時)に転職し『メタルギアソリッドV』の開発に参加。その後、マーザ・アニメーションプラネットに戻り10年間、映画・ゲーム・アニメ制作に従事。現在はSUPER PRIMEにAIアーティストとして所属し、AIと共に作品制作、表現研究を行っている。
令和7年度文部科学省の概算要求が発表され、高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)継続希望校・新規希望校は次年度に向けて企画や予算の検討をしています。同省は、2年目はハード購入ではなく、コンテンツ等のソフト面での充実を期待していると思われます。2年目の企画について、国の考え・高校現場の声をもとにポイントを解説します。

石川県内の公立高校、石川県教育委員会事務局を経て、2015年より文部科学省初等中等教育局 高等学校情報科教科調査官を務め、「情報I」「情報II」などの学習指導要領の取りまとめや、GIGAスクール構想、情報活用能力の育成などを担当。
2020年より大阪芸術大学アートサイエンス学科客員教授、2021年より京都精華大学メディア表現学部教授、情報活用能力調査委員、実教出版編集顧問、Life is Tech!株式会社顧問、SeckHack365実行委員長(情報通信研究機構主催)、2022年より(一社)デジタル人材共創連盟代表理事、2023年より、東京学芸大学講師、広島修道大学講師

1984年生まれ、岡山市出身。岡山学芸館高等学校スーパーVコース卒業、高校在学時は生徒会長。
早稲田大学・大学院を経て、民間のコンサルティング会社に勤め、2011年から同校の地歴公民・情報科の教員。
2019年より教頭、2023年から副校長を務めている。
文部科学省事業のSGH(スーバーグローバルハイスクール)、高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)の校内推進を担当。
2025年4月スタートの同校の通信制課程フレックスVコース(設置認可申請中)を立ち上げ、責任者を務める。
AI時代の到来が交差する今、デジタル化による新たな可能性と課題に直面しています。 本セッションでは、AI技術の活用方法、リモートワークやフリーランス人材の効果的な登用など、今直面する人材確保と働き方のアプローチを探ります。

リクルート入社後、総務、人事、新規事業開発等を経て、1999年ワークス研究所を立ち上げ、2013年より現職。厚生労働省雇用類似の働き方に関する検討会委員、東京都くらし方会議委員、日本テレワーク協会アドバイザーなどを歴任。労政記者クラブ所属。
軽食とドリンクをご用意し、登壇者の皆様と参加者による立食パーティーを行う予定です。
近未来教育フォーラムにご参加の方はぜひお気軽にお立ち寄りください。

会場
デジタルハリウッド大学 駿河台キャンパス
(東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティアカデミア3F)
最寄駅
JR「御茶ノ水駅」聖橋口より徒歩1分
東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」B2出口直結
東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩4分
JR「秋葉原駅」より徒歩9分
車でお越しのお客様
ソラシティ駐車場をはじめ会場周辺に一般駐車場はございますが、数に限りがございます。公共の交通機関をご利用ください。